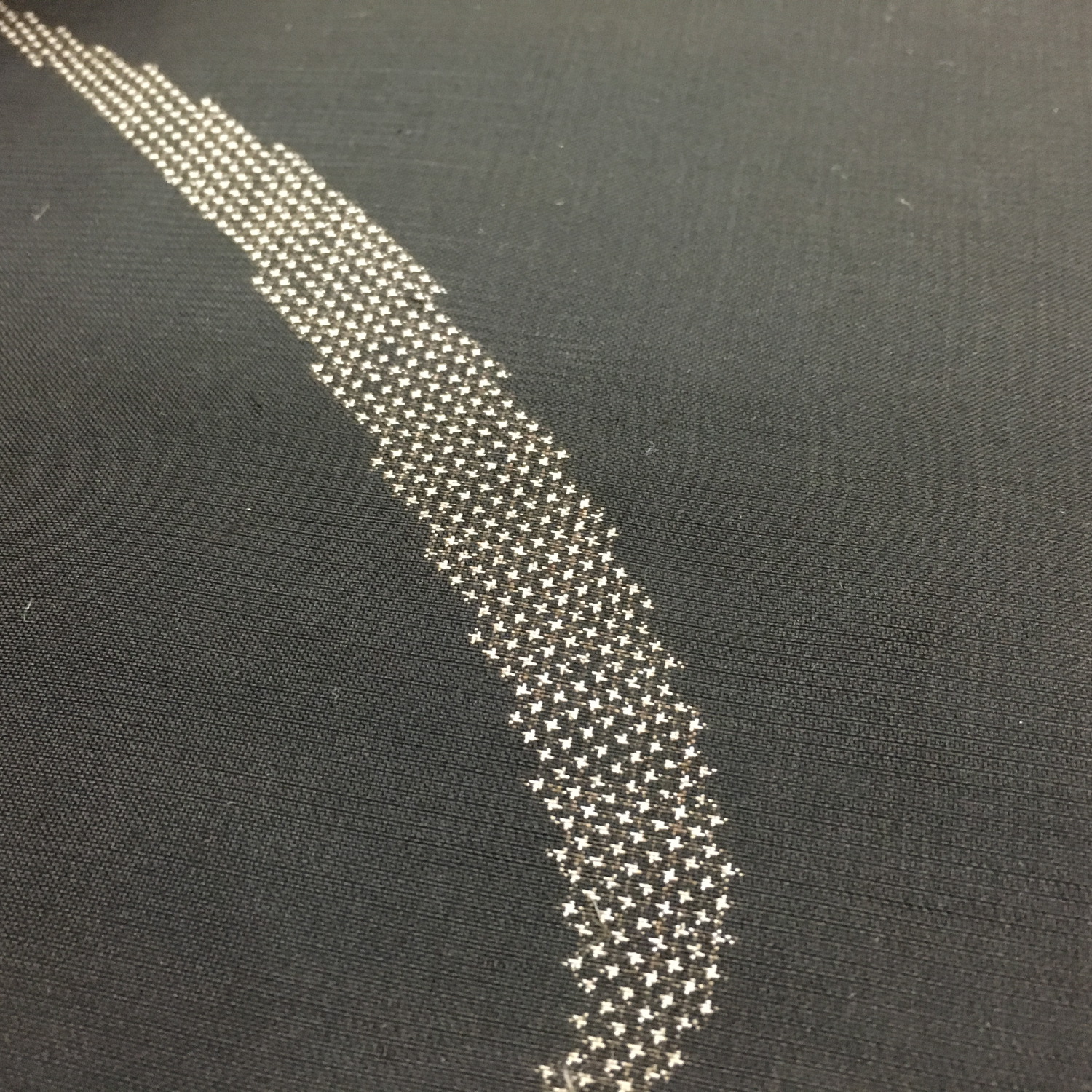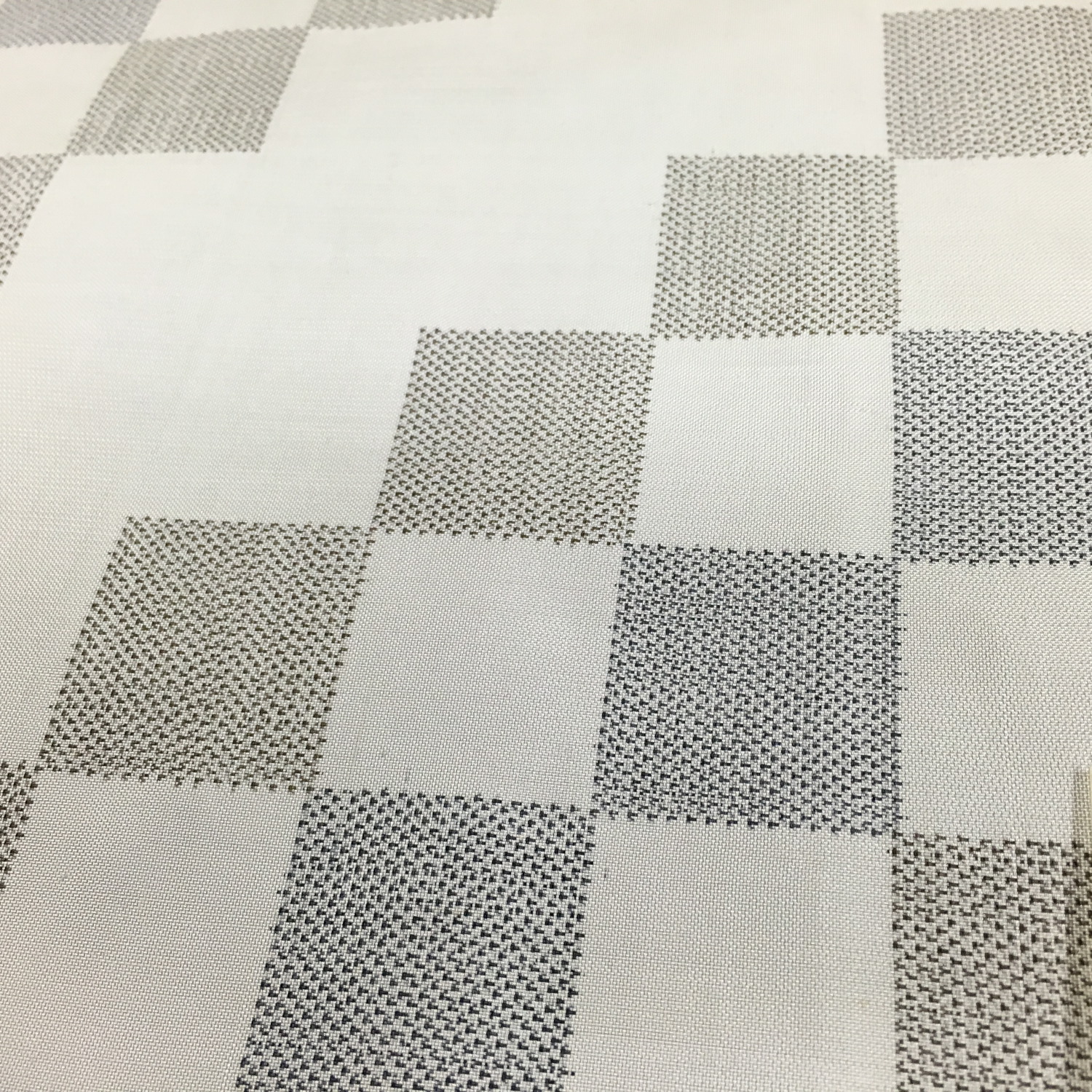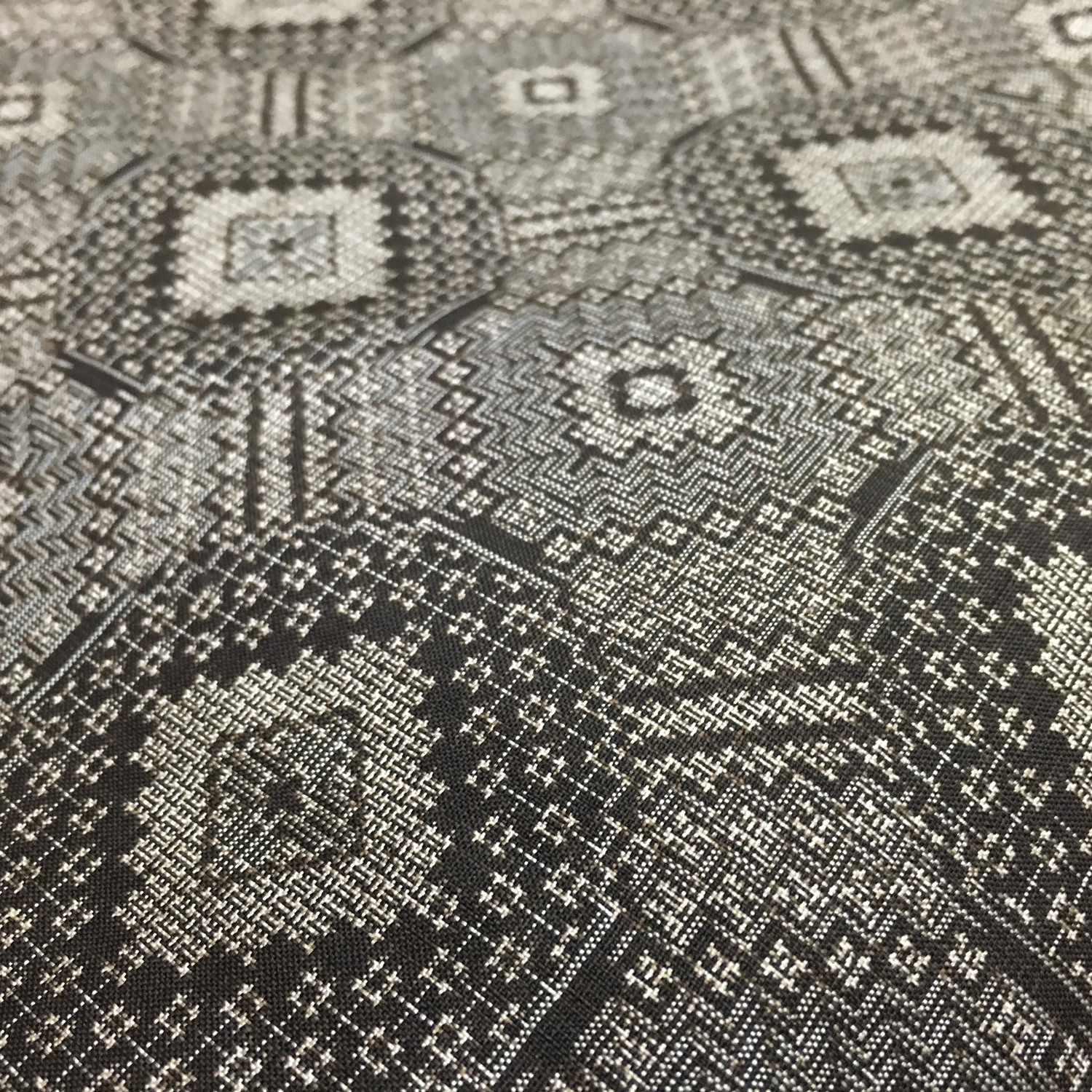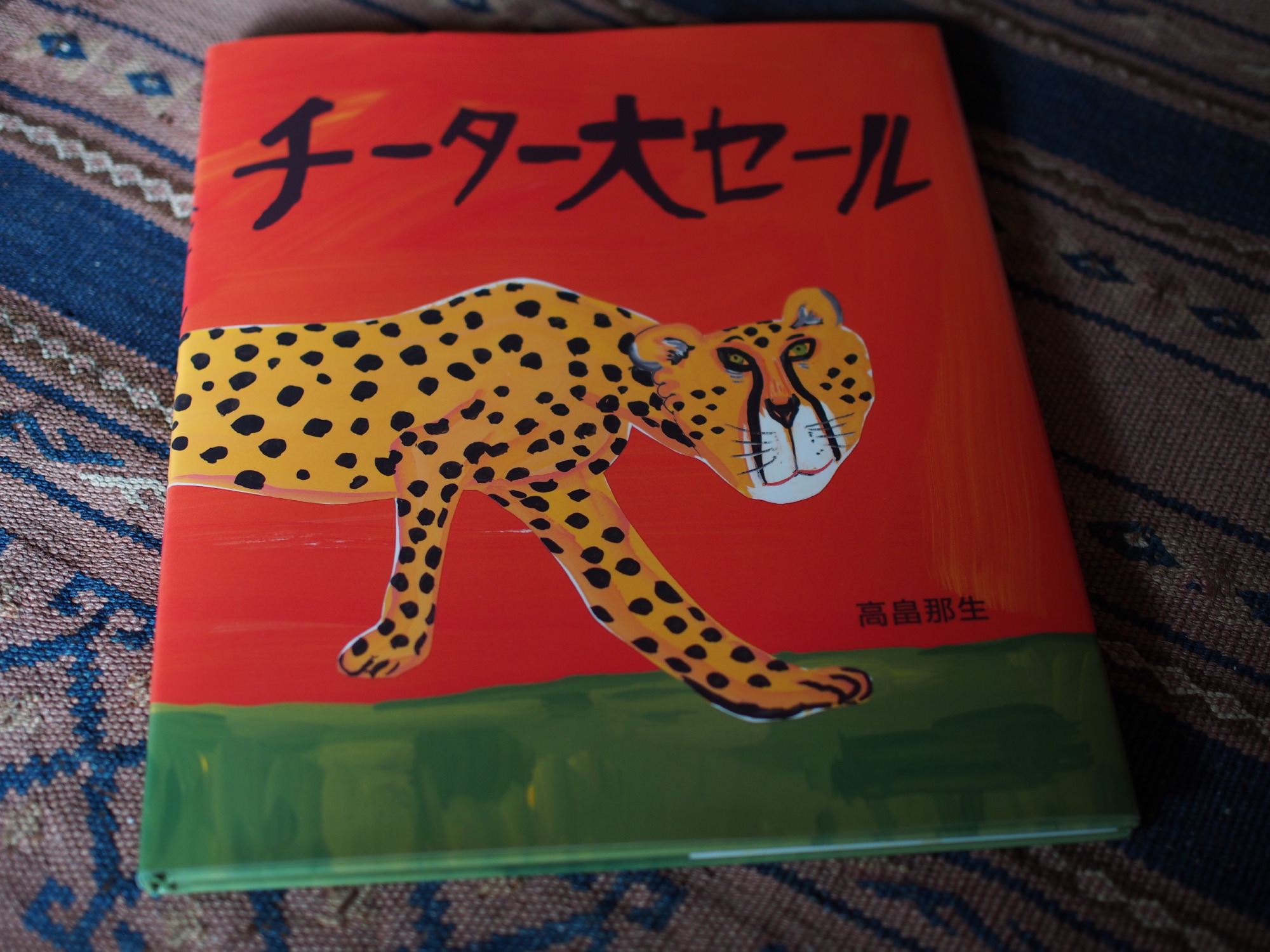悟りに向かう道は男女平等。しかしサンガでは男性のグループが上位。それはなぜかと言うと、まず釈迦は自分が救われるために修行をして悟りを開いた。その後、梵天に請われ、他の人々も助けようと立ち上がった。このときのターゲットが「自分と同じ行動ができる人」=「男性」。人気が出て女性もやって来るようになったが、最初は拒んでいた(「自分と同じ行動が都できる人」に当てはまらないから)。釈迦の育ての親マハーパジャパティーもやって来る。それでもなお女性を拒んでいた釈迦だったが、弟子のアナンが説得し、比丘尼サンガが誕生する。新しくできた女性の比丘尼サンガにはリーダーがいないので、半月に一度は比丘尼サンガが男性の比丘サンガに教えを受けるなど、幾つかのルールが決められ、「組織」としての差別ができた。
比丘尼サンガが成長し自立することができたら、組織としての差別は撤廃されたはず(先生曰く)。その前に釈迦がなくなってしまったので、差別が残った。日本は「律」がないので差別もない。
・無色界/肉体を持たないが心はある 非常に弱い煩悩/空中 神
・色界/初禅・二禅・三禅・四禅の四段階 肉体はある 欲望はない 煩悩はある/空中 神
・欲界/人間はここ/土があり歩けるところは全部欲界
煩悩は少しづつ消えていく(消す煩悩によって下記のようにステップアップ)
強い煩悩は消しやすい 弱い煩悩は消しにくい=極めて強い精神集中が必要
どの煩悩を消したかによって輪廻の場所が決まる
その段階のすべての欲望を消すとその場所には再び生まれず上のクラスに行く→不還(ノーリターン)
阿羅漢(「修道」によって上がる 色界・無色界が消える)
不還(「修道」によって上がる)
一来(「修道」によって上がる)
預流(ここから聖者「見道」によって上がる)
凡夫
悟りを開き(涅槃)人間として生まれない、つまり人口ゼロを目指したのが釈迦の仏教(ただし仏教というインド語はない。「道」が本質を表す言葉)
業(カルマ)がいつからあるのかはわからない=無始
仏教では「天」は役職名
バラモン教では神は死なない。バラモン教を部分的に受け入れ新しいものを作った
有限と思われていたものを全て無限とした。つまり仏教も滅びる、しかし再生するという考え方