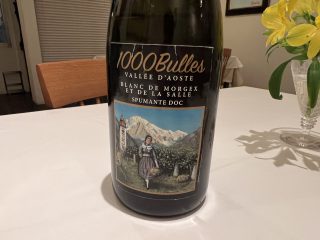先日、後水尾天皇の消息に触れる機会を得た。後水尾天皇といえば、上皇になられてから修学院離宮を造営された方ではないか。修学院離宮はお近く。されど未だ伺ったことがない。これは行かなくては!と思い立ち予約をして本日参観した次第。離宮は、なんで今まで来なかったのだろう、と深く思うほどに素晴らしい場所であった。桜の時期や紅葉の季節は予約も混むのでしょうが、この時期はお人も少なく、お天気にも恵まれ(ちょっと不思議な空模様)ゆるゆると見学させていただきました。されどご案内の職員の方がお若く健脚で、歩を進めるのが早い早い。私も脚には自信があるので、ついてはいけますが、素晴らしい庭内と建物、そして借景、もう少しゆるりと歩きたい。それに参加者にはご年配者も多いから多少の配慮は欲しいところ。これはご意見として何かの折に宮内庁に申し上げよう、と思ってサイトを確認したところアンケートがありました。さっそく回答。しかーし、選択式と記述式の設問があって「選択式」と言っているのに選ぶ回答がなく。Safariだから?と思ってGoogle Chromでも確認してみましたが、一緒でした。どうなってるんだろ???
とにもかくにも修学院離宮。素晴らしい場所でした。またぜひ伺おう。なお現在は楓橋の架け替え中の為、一部ルートが普段と異なっていることと、お池の水も通常より少なくなっているとのご説明あり。