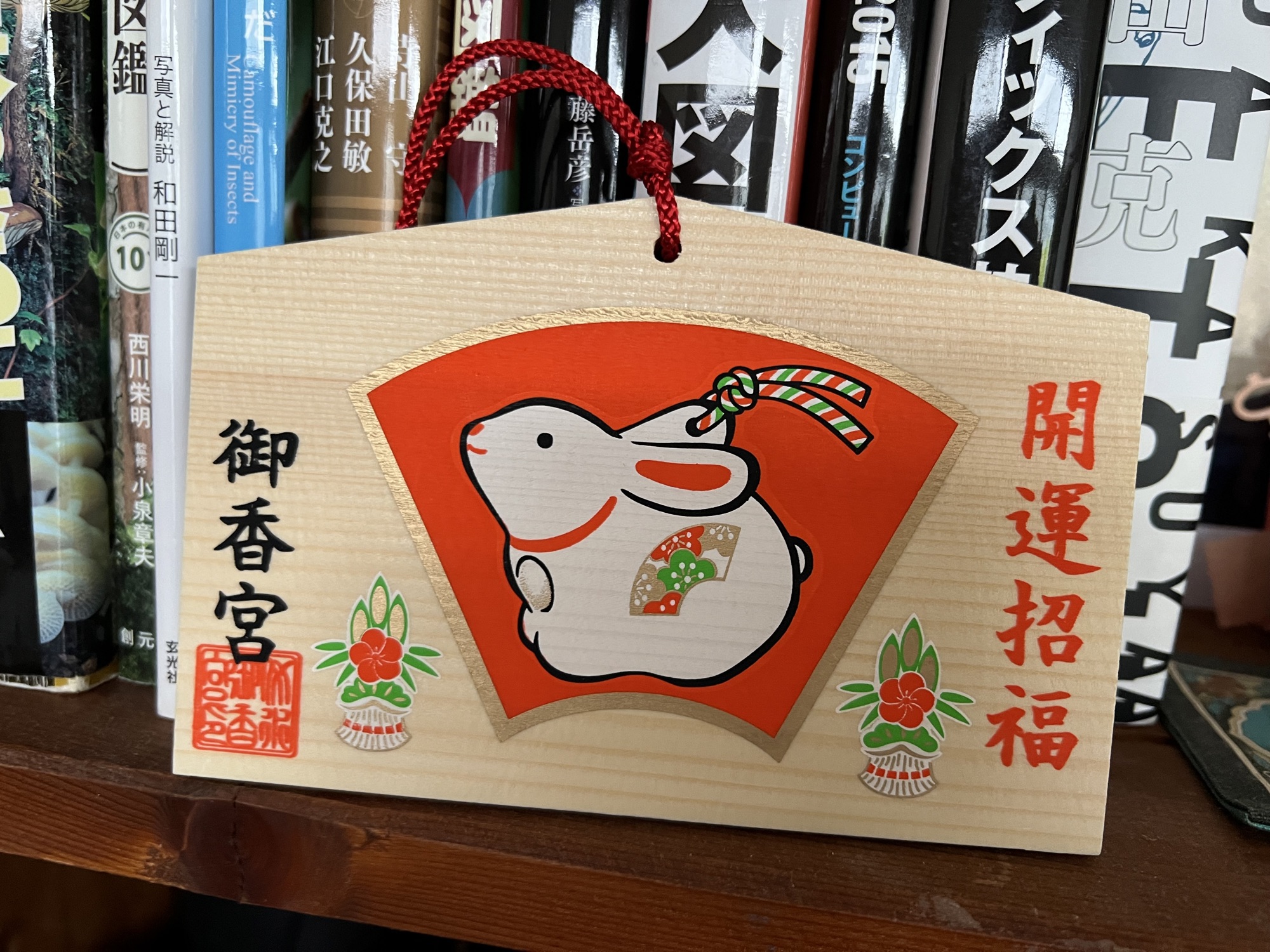初めて徳川美術館のお茶会に伺う。家を出るときは激しい雨脚。お茶会の途中から青空が広がり、雨に濡れた樹々と木漏れ日が美しい。がんばって早く起き、予定より早い新幹線に乗り10時前に美術館に到着できたものの、すでにかなりのお人がいらっしゃっているご様子で、11時55分の薄茶席からのスタートとなった。初めてでツレもなく勝手がわからずどきまぎしていたら、お稽古でご一緒の方が数名同じグループに。安堵。点心のお席が始まるまでまずは展示を見る。見応えがあり、後半はお茶席の後にすることにしてお点心。とても美味しゅうございました!その後、薄茶席、濃茶席と周り、最後に展覧席を拝見して、展示へ戻る。刀剣も数多く出ていたので「刀剣女子」もたくさんいらっしゃっていました。皆様熱心にご覧になっている。私は正直刀剣にはあまり興味が持てないので、袋だけ拝見してささっと通り過ぎる(笑)それにしても幾多のお宝に触れ、美味しいお茶とお菓子、点心をいただいて「スポーツの日」が素晴らしい「芸術の日」となった秋日。車中のコーヒーも秋でした。
初めて徳川美術館のお茶会に伺う。家を出るときは激しい雨脚。お茶会の途中から青空が広がり、雨に濡れた樹々と木漏れ日が美しい。がんばって早く起き、予定より早い新幹線に乗り10時前に美術館に到着できたものの、すでにかなりのお人がいらっしゃっているご様子で、11時55分の薄茶席からのスタートとなった。初めてでツレもなく勝手がわからずどきまぎしていたら、お稽古でご一緒の方が数名同じグループに。安堵。点心のお席が始まるまでまずは展示を見る。見応えがあり、後半はお茶席の後にすることにしてお点心。とても美味しゅうございました!その後、薄茶席、濃茶席と周り、最後に展覧席を拝見して、展示へ戻る。刀剣も数多く出ていたので「刀剣女子」もたくさんいらっしゃっていました。皆様熱心にご覧になっている。私は正直刀剣にはあまり興味が持てないので、袋だけ拝見してささっと通り過ぎる(笑)それにしても幾多のお宝に触れ、美味しいお茶とお菓子、点心をいただいて「スポーツの日」が素晴らしい「芸術の日」となった秋日。車中のコーヒーも秋でした。
以下、会記から転載(ただし表記スタイルには変更あり)
徳川茶会 主催 徳川美術館 表千家 名古屋長生会
・寄付 山ノ茶屋
床 茶道行儀書 通円筆
・本席 餘芳軒
床 竺仙梵僊墨蹟 示照侍者法語
伝来 七代将軍徳川家継ー尾張家六代徳川綱友
床脇 楓に鳳凰蒔絵 硯箱
花入 青磁 鳳凰耳
香合 堆朱 許由
香木 伽羅 銘 東大寺 十種名香の内
釜 雲龍
風炉 唐銅
長板 真塗
水指 砂張 鉄鉢 岡谷家寄贈
茶入 利休大棗 盛阿弥在銘 表千家六代覚々斎箱書 岡谷家寄贈
仕覆 格子堅縞間道
茶杓 千利休作 虫食 共筒
伝来 尾張家二代徳川光友
茶碗 大名物 三嶋桶
伝来 千利休ー千道安ー松花堂昭乗ー尾張家初代徳川義直
副 井戸
建水 唐銅 銀象嵌
蓋置 宣徳銅 三ツ人形
御茶 蓬左の昔 松柏園詰
菓子 銘 鶴聲 両口屋是清製
器 銘々皿 幸兵衛窯製
・副席 山ノ茶屋
床 尾張家二代徳川光友筆 遠浦帰帆図 小坂井家伝来
花入 伊賀 耳付 岡谷家寄贈
香合 独楽 朱塗
釜 繰口 葵紋 古浄味作
風炉 古銅 遊鐶
水指 備前 火襷 岡谷家寄贈
茶器 秋野蒔絵 中次
茶杓 一尾伊織作 共筒
茶碗 黒織部 沓
替 元贇焼 染付 文字文 木村克彦氏寄贈
建水 塗曲
蓋置 竹
御茶 初音 松柏園詰
菓子 芳光製
・道具飾席 宝善亭二階
床 武野紹鴎書状 常智宛 十一月三日
=====
*許由:中国,古伝説上の隠者。字(あざな)は武仲。聖帝尭(ぎよう)が自分に天下を譲るという話を聞き,耳がけがれたといって潁水(えいすい)で耳を洗い,箕山(きざん)に隠れたと伝えられる。
*元贇焼:江戸時代,明からの帰化人陳元贇が名古屋で製した陶器。安南風の染付陶器を瀬戸の陶土で焼いた。
【以上大辞林より】