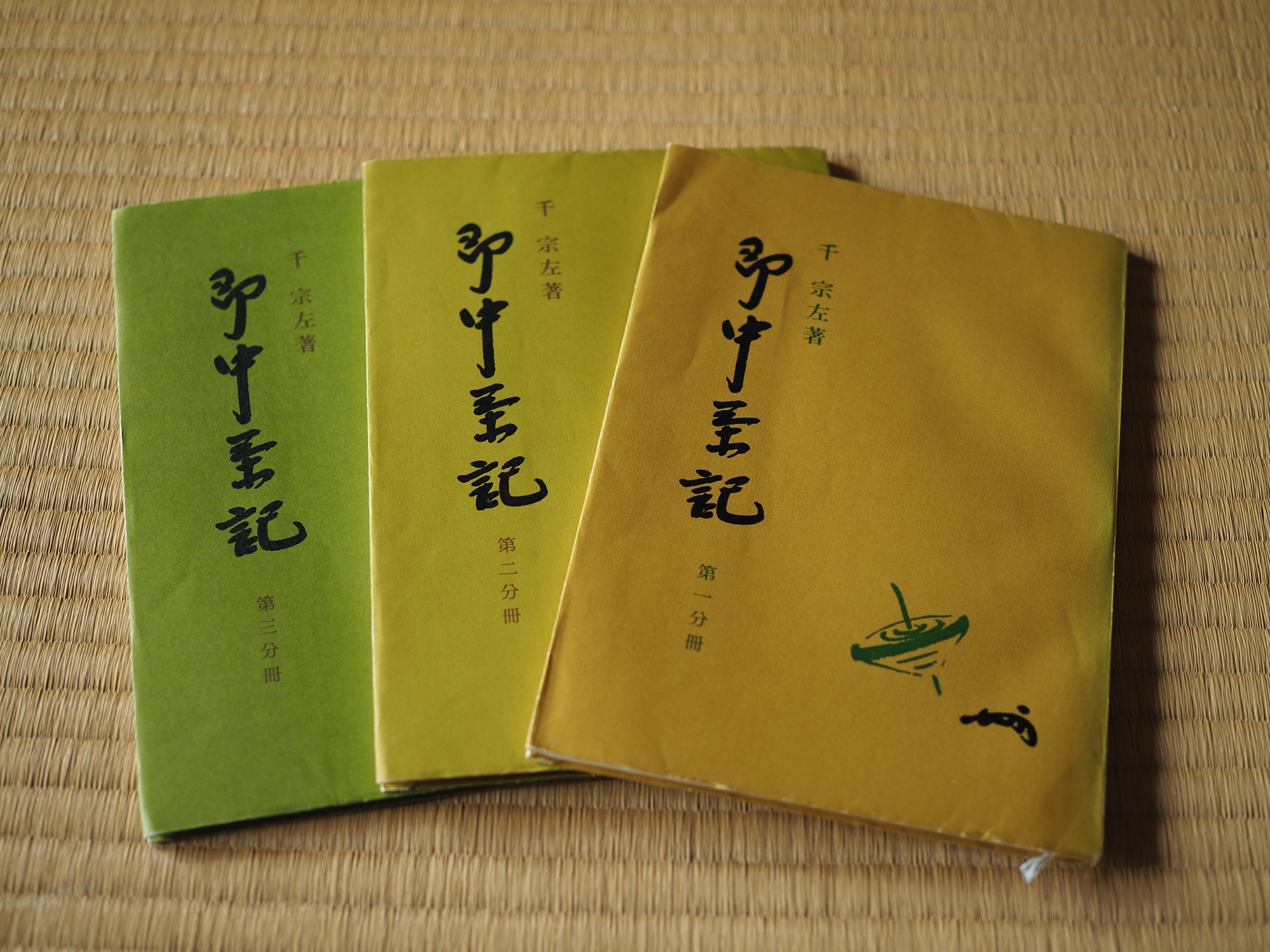表千家北山会館で開催中の特別展へ。猶有斎宗匠の御婚礼の節に整えられた「茶箱一式」に目が釘付け。代々受け継がれてきた表千家の茶湯、お稽古場で習う茶湯と自分が常の事として実践し得るもの、を考えつつ、家の仕事を受け継いで行くということ、などに思いを馳せながら拝見する。ご近所の古田織部美術館へも。北山会館のすぐ近くなのに、なぜかこれまで機会を逸していた。小さな小さな美術館ですが、展示品はすごい。昨日や今日、学び始めた訳ではないのに、未だ消息をちゃんと読めない。限られた時間の中で、ある程度文書を読めるようになりたいが、道険し(涙)「山上宗二記」の自筆を初めて見ることができた。几帳面な人柄が窺える。
移動した縄手通りで「八朔」の挨拶回りの舞妓ちゃんたちに遭遇。去年は中止だったものが2年振りに開催されたと帰宅してからのニュースで知る。私たちも夏着物。風もあり、想像よりは随分と凌ぎやすかった。
オーストラリア産トリュフに初めてお目文字した日にもなりました。