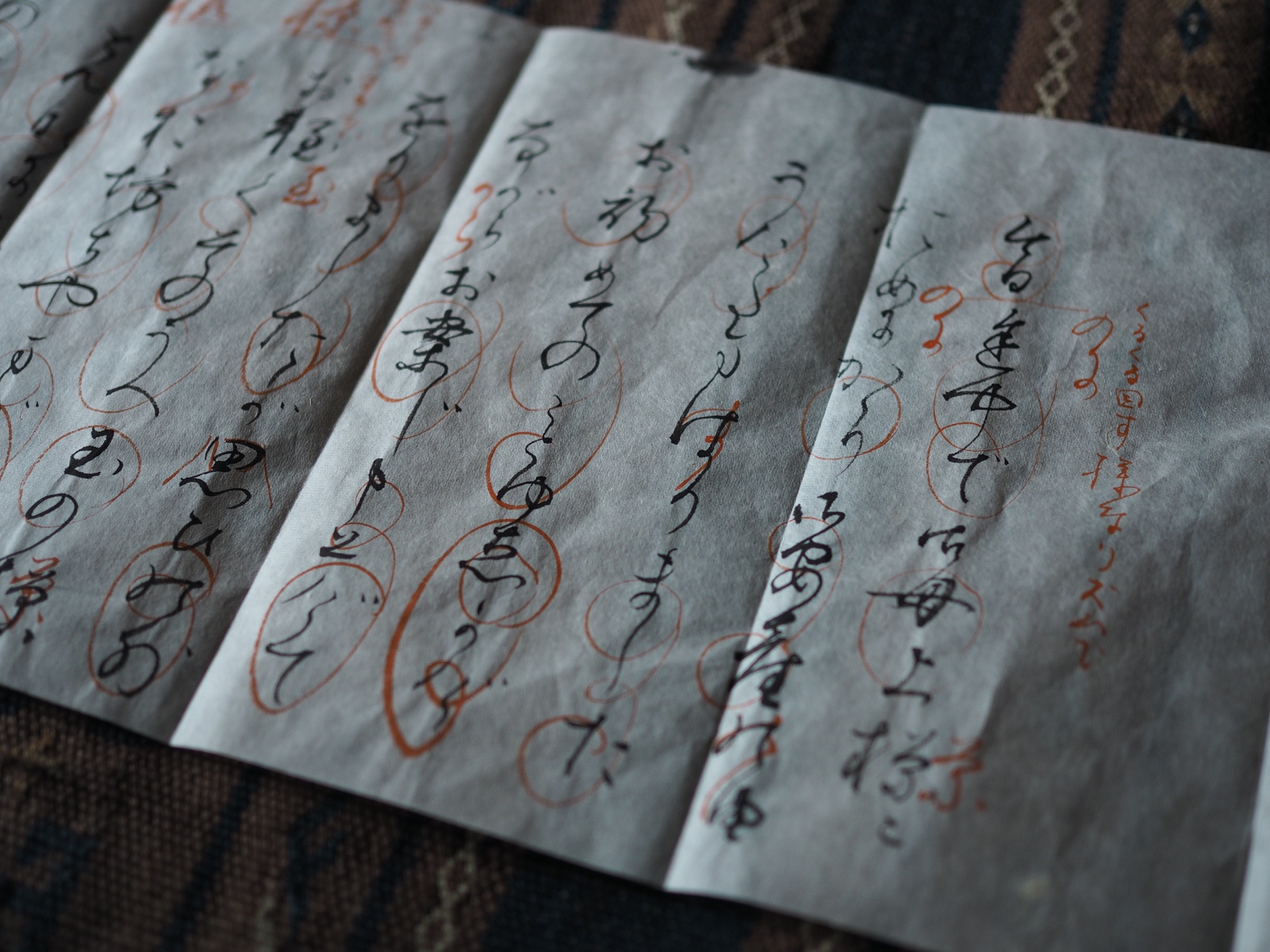“紫陽花の花の色は土壌が決めると言うけれど、そもそもなぜ花には色があるのか”
“紫陽花の花の色は土壌が決めると言うけれど、そもそもなぜ花には色があるのか”
「新型コロナウイルスー脅威を制する正しい知識」(水谷哲也著)に続き「免疫力を強くする 最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ」(宮坂昌之著)を読む。ワクチンに対してはよく知らないのになんとなく怖い、というイメージを持っている。まずはワクチンを正しく知らねばと、免疫学者である坂昌之氏のこの本を選んだ。一口にワクチンと言っても造り方もいろいろあり、それぞれに違った特徴があり、リスクもゼロではない、と教えられた。そもそもなぜワクチンが有効か、という初歩的なことも「抗体をつくれるから」ぐらいにしか分かっていなかったし「免疫」(自然免疫/獲得免疫)についてもしかり。そんな私にはたいへん勉強になった。それぞれの「ワクチン」を正しく知り、だったら摂取する摂取しない、と理性的に判断することに大いに役立つ内容だと思う。特に小さいお子さんをお持ちの方には読んでいただきたい。
さて、この本の中では「抗インフルエンザ薬の現状」にも頁が割かれていた。結論はあまり意味がなく“服用しても発熱期間が少し短くなるぐらいのものです。”とのこと。しかも薬の有効性が証明されているのは症状が出てから48時間以内に投与した場合に限定されるそうだ。2014年にインフルエンザBにかかり「タミフル」を処方されて飲んだ経験がある。このとき、身体中の痛みに耐えかねて病院を受診した。熱だけであれば、病院へは行かなかったと思う。思わず声が出てしまうほどの痛みで、それをどうにかしたいと思い、症状が出た翌日の朝、受診。担当してくれたDrにもその旨お話ししたが、検査をしてインフルエンザと診断されたら、自動的に「タミフル」が処方された。タミフルの服用で痛みも軽減されるかと思ったがそうはならず、たまりかねて夜間に再受診。Dr曰く、タミフルを処方したので痛み止めは出せない、ということだった。結局自然治癒を待つ他はなく、しかも服用したタミフルの副作用と思われる症状から立ち直るのにかなりの日数を要した。もう2度と飲むまいと心に決めていた「抗インフルエンザ薬」。さらにその意を強くする。いやその前に2度とインフルエンザにかからないようにしよう!