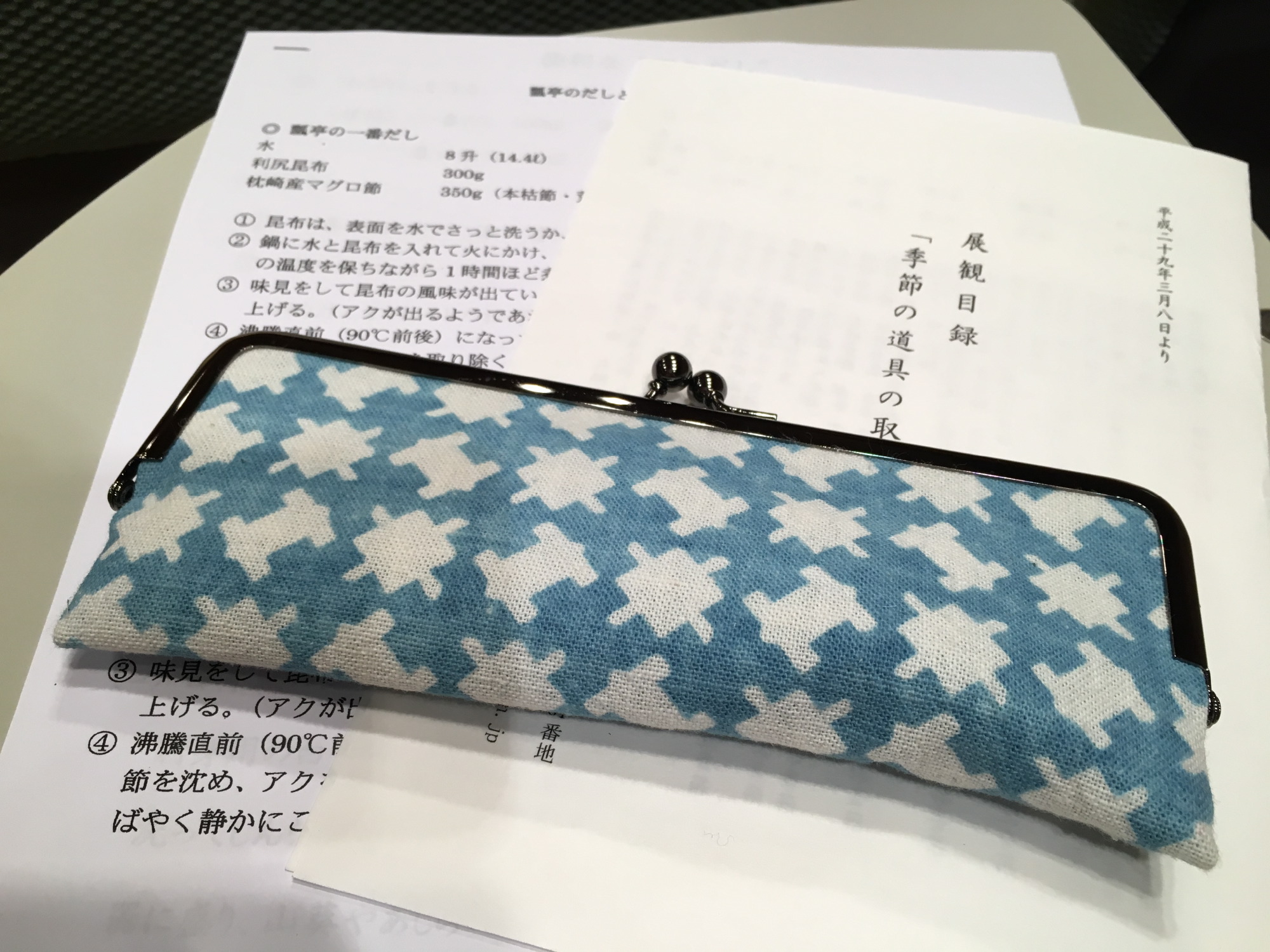昨日は雨にも負けず花冷えにも負けず、表千家北山会館主催の講座、“京都府立植物園の散策(二)「春爛漫の京都府立植物園」”へ伺った。講師は、京都府立植物園名誉園長、松谷茂さん。第一回へも参加してとても面白かったので今回も。例年だとソメイヨシノはすでに見頃を終えてしまっているけれど、今年は咲き始めが遅かったのでまだまだ見応えがあり、その後に続々と咲く八重紅枝垂、御衣黄、祇王寺祇女桜なども咲きそろい、見事。4月2日に続いての訪問で、またがらりと風情の違うお庭を堪能できた。植物園は本当に楽しい。
昨日は雨にも負けず花冷えにも負けず、表千家北山会館主催の講座、“京都府立植物園の散策(二)「春爛漫の京都府立植物園」”へ伺った。講師は、京都府立植物園名誉園長、松谷茂さん。第一回へも参加してとても面白かったので今回も。例年だとソメイヨシノはすでに見頃を終えてしまっているけれど、今年は咲き始めが遅かったのでまだまだ見応えがあり、その後に続々と咲く八重紅枝垂、御衣黄、祇王寺祇女桜なども咲きそろい、見事。4月2日に続いての訪問で、またがらりと風情の違うお庭を堪能できた。植物園は本当に楽しい。
しかしこの大正6年に開園された植物園。幾度かの危機があったらしい。近年サッカー競技場の候補にあがったことは知っていたけれど、1945年(昭和20年)連合軍に米軍家族住宅地として接収され翌年園内各所に将校住宅が建てられ、多くの樹木が伐採されたそうだ。当初は京都御苑が進駐軍の住宅地の候補だったものをそれはいくらなんでもと植物園が代替地になったとか。1957年(昭和32年)ようやく接収解除、1961年(昭和36年)に再公開。桜も接収されたときほとんど切られたようですが、何本かの大木は伐採を免れたもの。歴史の証人、いや証木ですね。皆に愛される今の植物園からは想像できない苦難の歴史があった植物園。折々に存続に尽力された方々に感謝しこれからも足を運ぼう。
さて、昨日は生憎の空模様。主に温室でのレクチャーおよびフィールドワークとなった。天皇皇后両陛下がご来臨あそばされたときのエピソードもお聞きすることができたいへん楽しく有意義な時間。珍しい花や実も数多く見られた。「学び」って楽しい!あぁ、学生の頃に気がついていれば(笑)
「シダレザクラ」
1)花
・花の色: 白 淡いピンク 濃いピンク
・花の枚数:一重=5枚 八重:10枚以上
・開花時期:ほぼソメイヨシノと同期かやや早い ソメイヨシノの後
*野生の桜、エドヒガンの枝垂性を品種化したものなので、花はまったく同じ
*花の大きな特徴は萼筒の基部が膨れること
2)幹のライン
*ソメイヨシノなどの桜の幹は普通、皮目(ヒモク)の横ラインが顕著
*エドヒガン=シダレザクラの幹の下部は縦にシワが入る(横の皮目が目立たない)
(以上当日の資料より)