





Photo by iPhone 5s/More photo
書の先生プレゼンツ、古梅園さん見学と「にぎり墨」体験&「ロウケツ染」体験、という贅沢な大人の体験学習の一日。近鉄を利用して奈良まで。JR組の先生たちと合流してまずは古梅園さんへ。こちらの佇まいを拝見しただけでテンションが一気に上がる。ステキスギ!
油煙墨の制作過程を順を追って見学。古梅園さんは最初から最後まで手作業。廉価な墨も高いものも作業は一緒。すべての工程を手作業で行っているところはもうこちらだけらしい。ケミカルなものが一切入らない墨作りは寒い時期だけに行われる。基本的には11月から4月いっぱい。ただしその間は毎日が重労働。さて、墨が作られるまでをざっとおさらい。
植物性油脂(現在は主に菜種油)を燃やして煤をとり、その煤を膠と混ぜて練り、木型(梨の木)で成形し、木灰に入れて約7割の水分を抜き、最後は吊るして自然乾燥させる。
もう少し詳しく記しておこう。
A 採煙:「油煙だき」と呼ばれるこの作業は、土蔵づくりの棟で行われる。かわらけ(土器)に油を入れいぐさの灯芯で燃やし、ハンドルのついたかわらけ『どうき』をかぶせ、その内側についた煤煙をとる。部屋に入ると真っ暗な中に炎がずらっと並び圧巻。一部屋に100個。同じ炎に保つため職人がたえず炎の加減に注意をはらい、1時間ごとに油を追加、15分ごとにハンドルつきかわらけを回して、均等に煤がつくように配慮する。そして2時間後、『どうき』の裏についた煤を羽ではき落として採取。これ日に4回繰り返す。
B 膠:煤と共に大切な材料の膠。壺(古いものは銅製、新しいものはステンレスだったか)に水と膠を入れ、70度程度のお湯で湯煎。
C 煤と膠ができたら「もみ」と呼ばれる作業。煤と膠を手でよく混ぜ合わせて練り、足でもむ。*もみ終わったものを職人さんはお尻に敷いていました
D もみ上がった墨は香りがつけられた後、木型(梨と決まっているそうだ)に入れられ成形。
E 木型から取り出された墨は、木灰に埋められ乾燥。一日目は水分の多い木灰、二日目以降は少しずつ水分の少ない木灰に埋め替えられる。小さいもので一週間、大きいもので30日から40日。この作業で約7割の水分が除かれる。その後、藁で編んで天井から吊るされ(黒い高野豆腐の様)室内で約半月から3ヶ月から自然乾燥させる。
F 乾燥が終わった墨は表面に付着した灰などを落とすため水洗い。艶を出すものは蛤の貝殻で磨かれる。
この日は三人の職人さんがEの作業をされていた。その工程をお聞きしてからその場所で”はい、にぎってみましょう“といきなり「にぎり墨」体験が行われた。へっ!?今ここで??とちょっと慌てふためく参加者一同(笑)中から職人さんが棒状の墨を手渡してくれる。それを利き手でぎゅっと強く握りしめて飛び出した墨を親指でぐっと押す。手が黒くなるかと思いきやほとんどまったくと言っていいほど、ならない。細かい質のいい煤だからだそうだ。今日は4千円と5千円の墨が作られていて、せっかくだからと全員5千円のグレード。生暖かい棒状の墨をぎゅっと握り混む作業はあっという間だったけれど、不思議な感触でとても楽しかった。握った墨は乾燥の工程を経て送られてくる。届くのが楽しみだ。
墨作りの職人になりたいと希望する若い人は意外に結構あるようですが、過酷な作業にほとんど続かないそうです。確かに「もみ」の作業ひとつ取っても非常に大変そうだ。この工程を他所では機械化しているようですが、機械で練ったものは均一過ぎて面白みにかける墨になるとか。もちろん考え方は色々あると思うけれど、たとえて言えば、機械織りの反物と手織りの反物の違いか。
墨作りを理解してからお買い物。いっそう墨が尊く思える。ほとんどが牛の膠を使用しているそうですが、山羊や鹿など他の動物の膠のものも。私は山羊の膠で作られた墨を購入。牛より膠がさらりとしていて仮名書きに向いている、というご説明でした。その違いが私にわかるかどうかは置いといて、チーズもシェーブル好きだから(笑)
「削り墨」という木型で固めるときに出る、いわゆる“バリ”の部分を袋詰めにした商品も。この「削り墨」という存在も初めて知る。主な需要は提灯屋さんだとか。「墨」を書道のものとしてだけではなく、素材の一つ、と位置づければもっと需要が広がるのではないだろうか。墨の美しさを、もっともっと多くの人に知ってもらいたい。そして墨作りの火が絶やされないことを切に願う。私も今まで以上に墨を大事に、そしてたくさん使おうと決意する。
お昼をはさんで午後は「ロウケツ染」ワークショップ。まさに大人の体験学習!+つづく+
 「にぎり墨」体験の次は染色家の中井由希子さんの工房で「ロウケツ染」ワークショップ。姉は確か中学生のとき美術の授業でロウケツ染をしていたけれど、私のときはなかった。絞り染や友禅の体験はありますが、ロウケツ染は初めて。楽しみです。でも不器用だからちょっと不安(笑)
「にぎり墨」体験の次は染色家の中井由希子さんの工房で「ロウケツ染」ワークショップ。姉は確か中学生のとき美術の授業でロウケツ染をしていたけれど、私のときはなかった。絞り染や友禅の体験はありますが、ロウケツ染は初めて。楽しみです。でも不器用だからちょっと不安(笑)





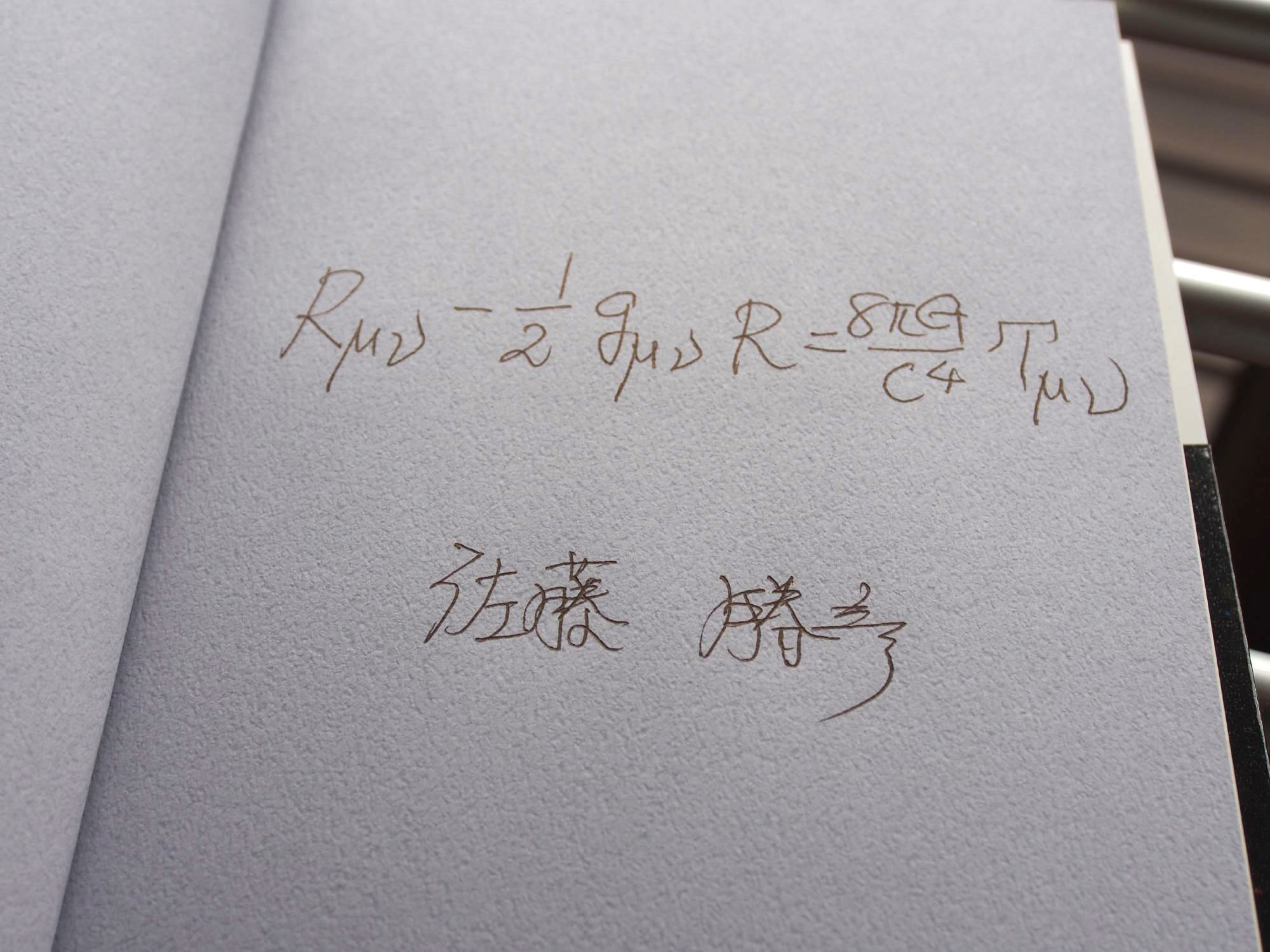

 2006年8月27日(日)に冷泉家の乞巧奠を拝見した。そのときの日記を転記。文章は当時のまま。
2006年8月27日(日)に冷泉家の乞巧奠を拝見した。そのときの日記を転記。文章は当時のまま。
 昆虫好きのやぎを真似して私も撮ってみました。「マーガレットコスモスとリトルヤブキリ」そして「シャガとリトルヤブキリ」。
昆虫好きのやぎを真似して私も撮ってみました。「マーガレットコスモスとリトルヤブキリ」そして「シャガとリトルヤブキリ」。