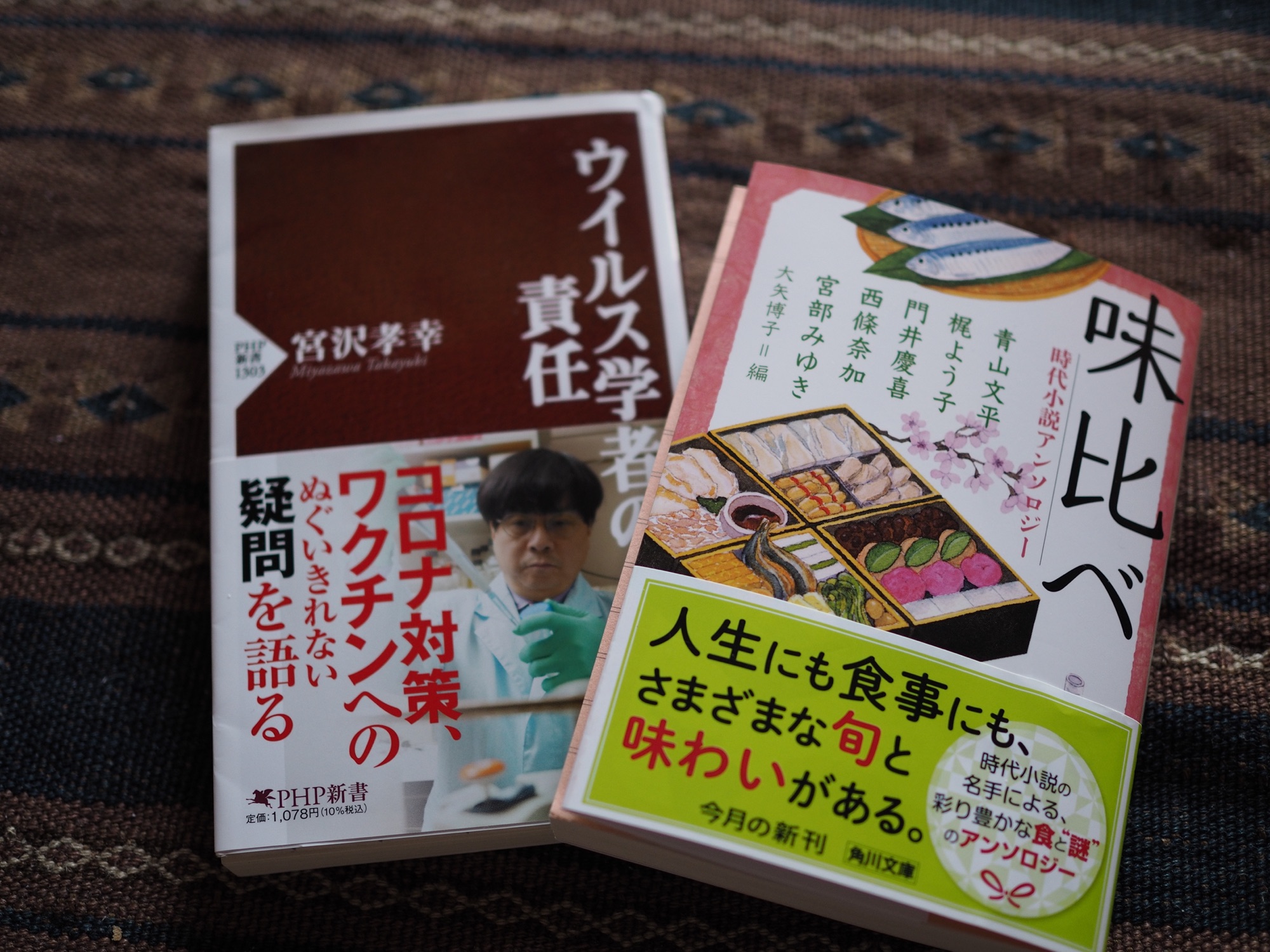縁側のテーブルに合わせてスツールを新調した。お願いしたのはテーブルを作っていただいた田中智章さん。ずっと手持ちの丸椅子を使っていたのが、お尻が痛くなりこれはもうダメだっと新しくオーダーすることにした。田中さんには本棚や食器棚などもお作りいただいているので、安心してお任せができる。メールで数回やり取りして座面の素材は革に決め(材はオーク)、田中さんが座面張りを依頼する村上椅子さんに出向いてサンプルを見てどの革でお願いするか決定。その折、座面のカーブも同じ型のものに座り確認。そして本日、村上椅子さんが、張り直しをお願いした他の椅子と共に搬入してくださいました。村上椅子さんも「痒い所に手の届く」お仕事ぶり。信頼してお願いができる方々が近くにいてくださるのは本当にありがたい。
縁側のテーブルに合わせてスツールを新調した。お願いしたのはテーブルを作っていただいた田中智章さん。ずっと手持ちの丸椅子を使っていたのが、お尻が痛くなりこれはもうダメだっと新しくオーダーすることにした。田中さんには本棚や食器棚などもお作りいただいているので、安心してお任せができる。メールで数回やり取りして座面の素材は革に決め(材はオーク)、田中さんが座面張りを依頼する村上椅子さんに出向いてサンプルを見てどの革でお願いするか決定。その折、座面のカーブも同じ型のものに座り確認。そして本日、村上椅子さんが、張り直しをお願いした他の椅子と共に搬入してくださいました。村上椅子さんも「痒い所に手の届く」お仕事ぶり。信頼してお願いができる方々が近くにいてくださるのは本当にありがたい。
以前は座面の硬さなどにそれほど留意していなかったけれど「大臀筋炎症事件」勃発後はずいぶんと神経質になった。大事なことは座ったときに骨盤がちゃんと立つことらしい。そのため座面の素材と硬さ、奥行き、床から座面までの高さなど慎重に検討すべきだ。そういえば昔、早稲田大学に出向いて最適な椅子の寸法を割り出してもらったことがあった。すっかり忘れていたけれどその時作成してもらったカルテを探し出してみた。今から20年前。カルテ制作者は早稲田大学区野呂研究室「チェアクリニック&デザインスタジオ」。確か被験者を募集しているのを何かで知って出かけたようにうっすらと記憶している。「自分の目的にあった最適の椅子の選定」としてオフィス、ダイニング、福祉用と解説があり、身体測定(身長、座高。下腿高、座位殿・膝窩距離)と体圧分布測定をした上で、私にとっての理想的な椅子環境がオフィス環境下、図で示されている。カルテ内の理論値が算出された式も載る。こんな大事なデータを仕舞い込んでいたなんて!次の機会には大いに参照しよう。ただし、仕事用の机と椅子は私専用なので理想の寸法にすることも可能だけれど、ダイニングなどはそうは行かない。とにもかくにも、理想的な椅子であっても同じ姿勢を続けることはよくないので、この点は大いに気をつけたい。つまり「落ち着きがない」方が身体にはよいことになるのだ。ふむ。