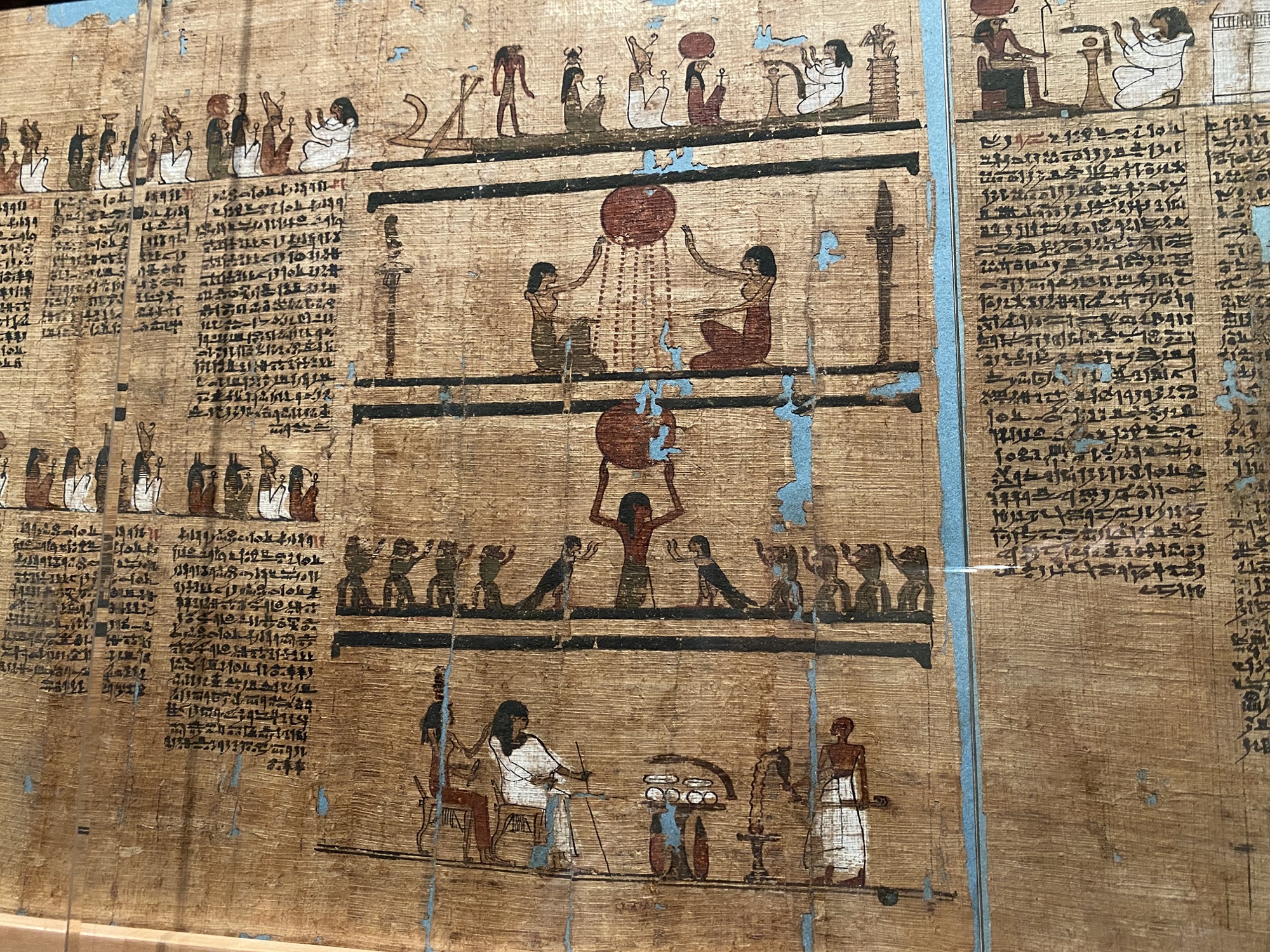王維*の詩『終南別業』。太字の部分をお軸で拝見することがある。「行雲流水」を思い浮かべた。こちらもお軸に書かれていることがある。禅宗の修行僧を雲水と呼ぶがそれも「行雲流水」という言葉に由来していると以前教わった。なぜか。“行雲流水のように淡々として一処に止往せず、天下に正師を求めて、遍歴する意よりくる。雲衲ともいう。数量的に大衆ともいう。”(臨済禅黄檗禅公式サイト「臨黄ネット」より)今は一箇所に留まって修行をするようですが、元々は師を求めて遊行(行脚)していたのですね。ちなみに「行雲流水」は蘇軾(1036年~1101年)の「謝民師推官与書」に出てくる言葉で「文を創る時の心構え」を示したものだそうだ。詳しくは福島みんなのニュースで。それがいつしか禅語になったということか。あるいは先に禅語として存在したのか。はたまた出典はまた別にあるのか。ちなみに王維は仏教(禅宗)に帰依。そして王維の生きた時代は中国で仏教が全盛をきわめていたそうだ。
中歳頗好道 晩家南山陲
興來毎獨往 勝事空自知
行到水窮處 坐看雲起時
(行いては至る水の窮まる処 坐しては看る雲の起こる時)
偶然値林叟 談笑無還期
*〔[701〜761]生没年は [699〜756] とも〕中国、盛唐**の詩人・画家。字(あざな)は摩詰(まきつ)。仏教に帰依し、詩仏と称され、また晩年の官名により王右丞(おうゆうじよう)とも呼ばれる。詩風は陶淵明に似、自然を歌詠した五言絶句にすぐれる。また、山水画を得意とし、後世、文人画(南宗画)の祖とされる。詩文集「王右丞集」など。
**中国文学史上,唐代を四分した第二期。玄宗の開元から代宗の永泰までの約50年間(713〜765)。唐詩の最盛期で、李白・杜甫・王維らが活躍した。
(スーパー大辞林より)
詩の訳などはNCS中国語教室のブログに詳しい。
禅語の解説、よいページを見つけました!臨済宗妙心寺派黄龍山西園寺のサイト内「今月の禅語」カルタがすてき。